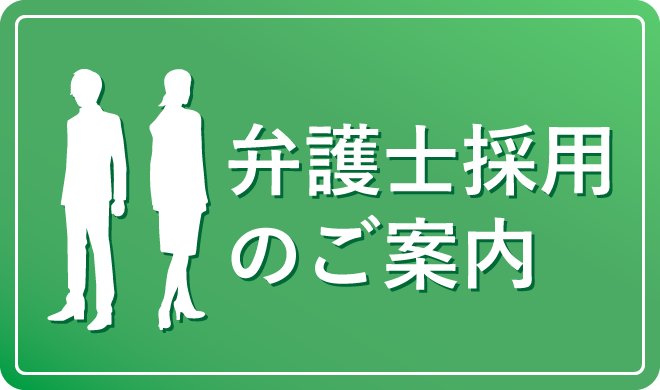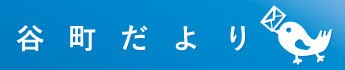12月7日(日)憲法ミュージカル「キジムナー」を観に行きました。 少しでも多くの人に憲法に触れてもらい、憲法について考えるきっかけになればという弁護士の思いから始まった試みが憲法ミュージカルです。毎回 …続きを読む
性犯罪や男女間で起きた暴力の被害を受けた人からの相談が絶えません。
近年の相談内容から、スマホが普及してSNSなどで簡単に他人と繋がることができるようになった影響もあり、小中学生といった子どもが犯罪やいじめに巻き込まれるケースが増えていることを感じます。
しかし、被害者が子どもである場合、親など周囲の大人に打ち明けることができず、被害が長期化し、何年も経過してから被害が発覚することも珍しくありません。
子どもに限らず、性被害者の半数以上が、誰にも相談していないことが統計から分かっており、被害の相談先を普及することが喫緊の課題として求められています。
更に、子どもの性被害が増えている現状から、性暴力の被害者・加害者を生まないための教育・啓発活動の重要さを改めて感じます。
独りよがりではなく、自他共に尊重しあう関係性を築くことの重要性を、幼少時から継続して教育していく「包括的性教育」が注目され始めていますが、現在の教育現場では、画一的な内容の性教育にとどまっているのが現状です。
福岡県では、平成31年に「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民を守るための条例」が制定され、性暴力を根絶するための教育施策や相談体制の構築など、様々な取り組みが行われています。
大阪府でも、被害が起きてからの支援だけでなく、性暴力そのものをなくしていくために、何ができるのか。模索しているところです。