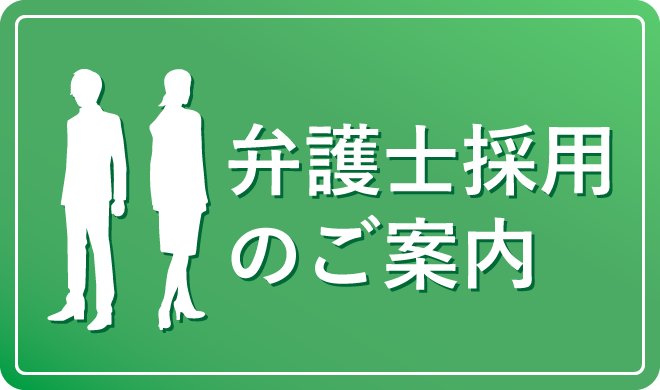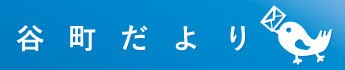弁護士というと刑事裁判では被告人を弁護するものと思われていますが、犯罪被害者を支援することも弁護士の重要な役割です。 今年の1月13日から、犯罪被害者やその遺族に対し、弁護士が公費で包括的な支援をする …続きを読む
5月3日は憲法施行の日。なぜこの日になったのでしょうか。当時の法制局長官の回想によれば、5月初め頃で、いくつか候補がありました。

「5月1日にするとメーデーだから実際上面白くない。5月5日は端午の節句で覚えやすいが、男子の節句であり武のまつりなので、男女平等・戦争放棄の憲法に相応しくない。それでは5月3日にしよう」ということだったそうです。
団結権を保障した憲法なので、労働者の祭日である5月1日を施行日とするのは良いアイデアなのではと思いますが、そうすると、現在の3連休は無かったかもしれません。
憲法施行は昭和22年で、翌年昭和23年に休日法が定められ、5月3日が憲法記念日として祝日・休日とされました。
ちなみに施行6ヶ月前の昭和21年11月3日が公布日です。公布日と施行日のいずれを憲法記念日にするか、衆議院と参議院で意見が分かれ、最終的に施行日になりました。