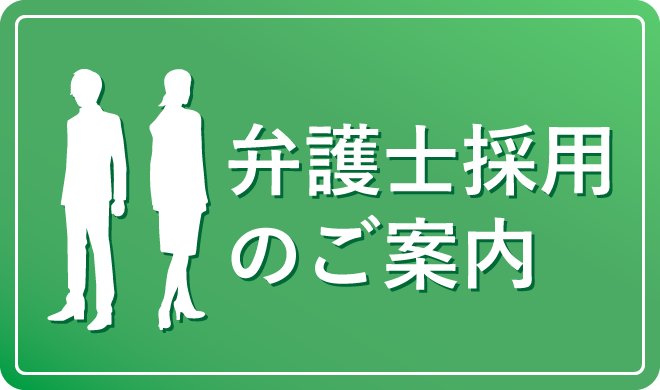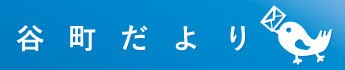2023年9月から2025年8月までの2年間、民主法律協会の事務局長として、団体の運営に携わりました。 民主法律協会(略して「民法協」)は1956年に設立され、大阪を中心に法律家(弁護士や研究者)・労 …続きを読む
第2 遺言
それでは遺言には何を記載すればよいのでしょうか。
1 遺言として法的効力が認められるのは、自分の財産を誰にどれだけ残すのかということです。「兄弟仲良くすること」といった遺訓のようなものや、遺言を書く理由には法的効力がありませんが、遺産分割の際にもめ事を減らすためには役に立ちます。
2 遺言を作成するには、自分の財産を正確に把握しておくことがまず必要です。
不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)、預貯金は通帳、株式は取引報告書などで確認します。自動車、生命保険、高価な動産についても確認し、目録にしておくとよいでしょう。借金や住宅ローンなど負債も、把握しておきましょう。
3 遺言の内容としては、まずは大まかな相続のさせ方を決めます。誰にどのような割合で相続させるのか、不動産や自動車、預金などの個別の財産を誰に相続させるのか、また、相続人以外の人(世話になった人や慈善団体など)に「遺贈」(いぞう)するのか、などです。
そして、法定相続分とは異なる内容の遺言を作成する際には、何故そうするのかの理由を書いておく方が良いでしょう。遺留分(後に述べます。)が侵害される相続人が現れる場合には特に注意が必要です。
4 遺言内容をスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定しておくことが有益です。遺言執行者は相続人の個別の同意なしに不動産の名義変更や、預金の解約、財産の分配などを行なうことができるからです。
遺言執行者は相続人の一人を指定することもできますが、複雑な場合や争いが生じそうな場合には弁護士を指定する方が安心です。
5 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(いりゅうぶん)があります。遺留分は相続人の最低保障部分のことで、それを侵害する遺言を作成すると、侵害された遺留分相当額を支払うよう請求されることが予想されますので、遺言を作成する際には、遺留分を侵害しない内容にしたり、侵害される相続人が納得できるような説明を施したり、支払いを請求される場合に備えて遺留分を現金にしておいたりする方策が有益です。