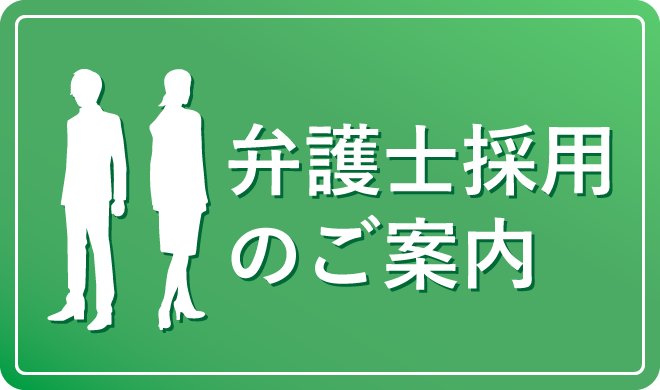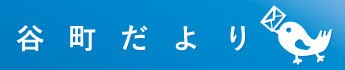顧問をさせていただいている大阪いずみ市民生協の勝山暢夫理事長からお誘いを受けて、昨年9月、大阪府生協連が主催する「福島第一原発等視察研修」に参加させていただきました。 こちらをクリックし …続きを読む
太陽光発電事業者が住民を提訴
ある業者が、淡路島(兵庫県)ののどかな集落の中心にある寺社のご神体の山を切り拓いて太陽光発電所を建設する計画を立て、地権者を籠絡して発電所用地の賃貸貸借契約を締結した。しかし、これを知った周辺の住民は大反対。送配電線(高圧電線)の確保もしないままずさんな計画で突き進んでいたその業者は、そこで行き詰まってしまった(発電所用地は公道には接しているが狭くて電柱が立てられないらしい)。住民の理解も得ないまま、ずさんな計画で突っ走ったのがいけないのだから、あきらめて撤退すればいいものを、なんとその業者は、送配電線設置を拒む土地所有者の住民を被告として、設置工事を妨害するなという裁判を起こしてきた。
民法213条の2
その業者が根拠としたのが令和3年改正により新設された民法213条の2である。同条第1項は次のとおり定める。
「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付…を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる」。
読んで字のごとく、これは電気、ガス、水道などのライフライン(電話・ネット等の通信回線も含まれるだろう)確保のためのものである。
ところが、業者は、同条は、発電された電気を送る高圧電線にも類推適用されると主張した。また、太陽光発電所は機械設備(パワーコンディショナー、連系用屋外キュービクル)の待機電力として常時電気供給を受ける必要があるから、これはライフラインであるとも主張した。
控訴審を引受ける
1審で住民側代理人を担当された地元の弁護士さんは、こんなものは到底認められないと信じておられた。ところが、あにはからんや、1審判決(神戸地洲本支判令和5年11月7日判例集未登載)は、業者の主張を認めて請求を認容してしまったのである。予期せぬ敗訴に住民側は大ショック。おそらくその弁護士さんもショックを受けられたとみえ、控訴審の受任は辞退された。とりあえず控訴だけはしたものの、途方に暮れた住民は大阪のいくつかの法律事務所を訪ね歩かれた末、2023年末に私のところに相談に来られた。これもご縁ということで、控訴審は当事務所の若手のエース・加苅匠弁護士と二人で担当することになった。
大阪高裁における審理
控訴理由書の骨子は、①太陽光発電所の送配電線はライフラインではなく、こんなものに民法213条の2を類推適用したのは間違っている、②仮に同条の類推適用があるとしても、損害の最も少ないルートが選択されるべきところ(同条第2項)、そうした検討もなされていないなどとした。すると大阪高裁から、第1回弁論に先立ち進行協議期日をもうけるとの連絡があり、そこで主任裁判官から、高裁として初の判断となるので、しっかり判断したい、ついては(執筆者の主観の入った)解説書ではなく、立法過程の資料(法制審の議事録など)を提出するよう求められた。
また、②については、住民に現地を案内してもらい、地図上にいくつものルートが考えられることを示して(ちょっと眺めるだけで10個近いルート案が考えられた)、土地所有者の損害がより少ないルートが他にあることを明らかにした(この論点は、同条が明らかに適用される場面でも判断の難しいものとなるだろう)。
ところで、これだけだと純然たる法律問題だけになってしまう。実際、1審では当事者の陳述書も提出されず、人証調べも行われていなかった。しかし、紛争の実態を具体的に浮き彫りにするのが私たちのたたかい方であったはず。そこで住民の中核的役割を担っている方の詳細な陳述書を作成して、その業者がいかに住民の意向を軽んじてきたかを明らかにした。すると、業者側は、その中核的人物が、自分の私的な利益のために住民を扇動しているという誹謗中傷に及んできた。おそらくは住民側に亀裂を入れようとしたのだろう。しかしながら、それまで住民側の理解を求めるべく誠実な努力をしたこともない業者が誹謗中傷に及んだからといって、住民側の結束にひびが入ることはなかった。
第1回口頭弁論では裁判長から業者側代理人に立て続けに質問が投げかけられ、他方で②の論点について反論したいという業者側代理人の発言に対してはその必要があるのかと言わんばかりの発言がなされたことから、私たちは逆転勝利をほぼ確信した。もっとも、油断は禁物。追撃の準備書面提出は忘れなかった。
大阪高裁の審理は弁論2回で結審した。人証申請は却下されたが、陳述書で紛争の実情は伝えたので、目的は達している。その後、敗訴を覚悟した業者側から必死の和解申入れがなされたが、自治会に寄付をするので業者の計画通りに認めてほしいという内容では、和解が成立するはずもなく、判決を迎えることになった。
大阪高裁で逆転勝利
大阪高裁判決(大阪高判令和6年8月22日判例集未登載。裁判長裁判官 長谷川浩二、裁判官 山地修、真鍋麻子)は、本件工事は発電した電気を送出するのが主目的であると指摘した上で、民法213条の2は「継続的給付を行う事業者に権利を認めるものではなく、事業者が多数の顧客に継続的給付を実施するための施設を設置すること(従来は地役権や区分地上権などによって賄われてきた、高圧電線を通すための鉄塔の設置など)は、基本的にこの規律の対象ではない」などとして、業者の主張を退けた。
さらに、「本件の紛争が生じた原因は、被控訴人(=業者)が発電した電気を外部に送るための経路を十分に検討しないまま土地を賃借して太陽光発電事業を行おうと計画したことにある」とまで指摘している。これはまさに私たちが強調していたことであった。
その後、業者は上告受理申立をすることなく、判決は確定した。早く判例雑誌に掲載してほしいところである。なお、その後、現地の動きはないようである。
玉石混交の太陽光発電事業
太陽光発電所は、クリーンエネルギーの象徴のように思われているが、儲かるとふんでいろんな業者が参入してくるからか、まさに玉石混交状態である。最近では、問題のある事例も報道されるようになってきた。本件でも、現地を案内してもらったところ、周辺にいくつもの太陽光発電所が設置されているのが目に入り、反射光が迷惑だとか、雑草伸び放題でイノシシが住み着いて困るなどの話も聞いた。結局は、田舎を踏みつけにしているわけで、その基本構造は原発と変わらない。そうした業者の横暴を食い止めた一事例であった。